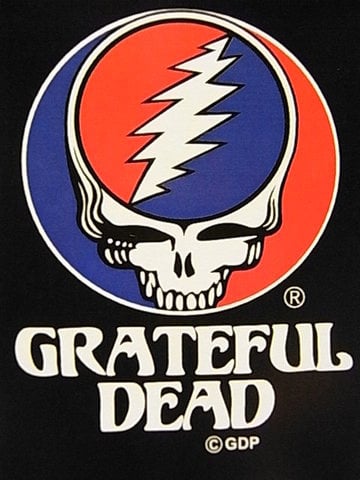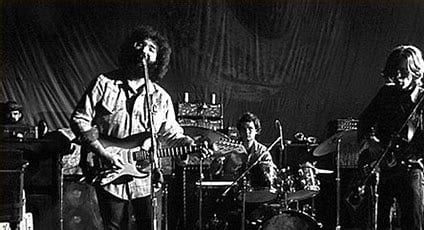ブログ
グレイトフル・デッドからマーケティングを学んでみる
2020-06-18
カテゴリ:音楽のお話
第3回!ロック啓発活動を開催

参考書物 「グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ」
(著)デイヴィット・ミーアマン・スコット+ブライアン・ハリガン
渡辺由香里訳 監修 糸井重里
【初 め に 】
ご紹介致しますバンドは、アメリカのサンフランシスコ出身で1965年に誕生し、1995年解散のバンドの「グレイトフル・デッド」でございます
上のドクロはバンドの有名なロゴマークの「スティール・ユア・フェイス」ですね 
 このロゴは知ってるって方は多いのではないでしょうか??
このロゴは知ってるって方は多いのではないでしょうか??
【にわかファン?】
実は私もそんなにこのバンドに関しましては詳しくはございません 日本で開催したラグビーワールドカップからラグビーを見てその期間だけ本気で応援してた程度の低い「にわかファン」かもしれません
日本で開催したラグビーワールドカップからラグビーを見てその期間だけ本気で応援してた程度の低い「にわかファン」かもしれません
【何故にグレイトフル・デッド?】
では何故このバンドを取り上げたかと言いますと、このバンドの活動として実に興味深いのは、音楽性も素晴らしいのですが「独自のマーケティング」を行って成功したバンドとして有名なのです 
このグレイトフル・デッドですが、日本国内においては馴染みは少なく、マニアックなバンドのイメージは強いと思います しかし、アメリカ国内では伝説のバンドとして知名度は高く、1994年には「ロックの殿堂入り」を果たしております
しかし、アメリカ国内では伝説のバンドとして知名度は高く、1994年には「ロックの殿堂入り」を果たしております
特徴は、大きなヒットアルバムがある訳でも無く、ライブバンドとして活動し、コンサート収益はアメリカ国内でも1.2を争う存在だったそうです
では何故「独自のマーケティング」で成功に至ったのでしょうか
グレイトフル・デッドが如何に成功を収めてたのかを、このバンドが行った事例をもとに「グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ」を読んで重要と考えた部分を抜粋して考えてみたいと思います

1.ユニークなビジネスモデルをつくる
グレイトフル・デッドは 確かにアメリカ本土でも大きなヒットアルバムは誕生してないにも関わらず、このバンドの熱狂的なファン「デッドヘッズ」を引き連れアメリカ全土をツアーで回り、ツアーキャラバンを行っておりました。
通常のバンド活動で主な収入源はアルバムを売る事で、そのアルバムを売る為にツアーに出かけて、そのアルバムの曲を中心に演奏するのが常識とされてますよね
しかし、グレイトフル・デッドはレコードの収益よりもツアーで得る収益の方が大きく上回り、アメリカ国内でも年間収益は1、2位を争う存在だったそうです  間違いなくグレイトフル・デッドは常識を覆し、ライブで稼ぐバンドとしての先駆けバンドとして活動を行っていた訳です
間違いなくグレイトフル・デッドは常識を覆し、ライブで稼ぐバンドとしての先駆けバンドとして活動を行っていた訳です
グレイトフル・デッドが誕生した時代背景
当時はヒッピーとサイケデリック文化が急速に広まる中でその文化と密接に交流を結び、その時代の代表的なバンドとして人気を得ます。グレイトフルデッドが誕生した年にはベトナム戦争の勃発で、戦場は激しさを増し、公民権運動は頂点にありました。
1967年にファーストアルバムを発売し、1967年にモントレー・ポップ・フェスティバルに出演(ロックフェスの元祖)・1969年に伝説となったヒッピーの祭典「ウッドストック・フェスティバル」へ参加し、更に人気を集め、数多くのバンドが支持を失う中でも、70年代~95年まで活動を続けて新しいファンを獲得し続けました (95年にバンドリーダーのジェリー・ガルシアが亡くなり解散)
(95年にバンドリーダーのジェリー・ガルシアが亡くなり解散)
活動30年のうちにアルバムを13枚発表し、500曲を演奏した内のオリジナル曲は150曲程だったそうです
それ以外はカバー曲だったとの事で、いかにこのバンドの幅の広いバリエーションとアレンジ能力の高さがあったが伺えます
そして、毎回違う曲目の演奏をライブで行こなっていたそうなので、観客は毎回新しい体験をする事が出来た訳で、1年に100回ある全てのライブを見に行くファンも少なくなかったそうです
1曲の演奏中に即興のセッションが入り10分以上になる事も普通にあったそうですので、1曲だけ見ても毎回違う体験を観客に提供していた訳ですね!
活動期間中のライブ数は2,300以上こなしたそうですが、リーダーのジェリー・ガルシアはなんと80%は即興で、20%が曲に順じた演奏をしたと言っていたそうなので、驚きです 良い意味でゆるい活動を行ってたんですね
良い意味でゆるい活動を行ってたんですね
「いきなりですがここからが本題に入ります 」
なぜグレイトフルデッドは、レコードよりもライブの収益が上回り、アメリカ国内で、1.2を争う収益を得れたのか
それにはこのバンドがファンに対する深い愛情を持って接していた事が大きかったようです
もともとヒッピー出身のメンバーで、お金目的で結成されたバンドでは無かったって事ですよね!ヒッピーの 合言葉は「ラヴ&ピース」な訳で、この精神は解散するまでファンを裏切る事は無かったようです ではどのようにファンに接していたかをご紹介したいと思います
ではどのようにファンに接していたかをご紹介したいと思います

1.ライブに来たファンには自由に演奏を録音をさせ、手作りのテープをファン同士が交換しあう事を許した。
これは現在の「フリーアプリ等」に該当する考えですね。また、テープの録音を許した事により、パワフルな口コミ・ネットワークが生まれました。その事によりファンを拡大させ、チケットを何億ドルも売り、この時代の最も象徴的なロックバンドになったそうです。この事を続ける事により、レコードを売る事に重点を置くのでは無く、ライブで稼ぐ「ビジネスモデル」を革新し独自のマーケティングを開拓して行った訳です。
2.消費者へ直接チケットを販売する。
グレイトフル・デッドは、ツアー情報をいち早くファンに知らせる為に1970年代初頭に会報を始めたそうです。自前のチケット販売事務所を作る事により、最も熱心なファンへ優先的に良い席を提供したそうです。ファンとのコミュニティを築き、ファンへ敬意を持って扱う事が、より熱心なファンになってくれる事をこのバンドは教えてくれます。
3.たくさんの熱心なファンを作る
普通のバンドは、自分たちがイメージするライブを観客へ押し付ける事が多いと感じます。
しかし、グレイトフル・デッドの考えは、2万人のファンもライブ体験の一部として扱い、ファンはバンドのライブを単なるコンサートでは無く、非日常的な「ハプニング」であり、冒険の旅の最終「目的地」として扱ったそうです。グレイトフルデッドの場合はバンド側の考えをファンに押し付けるのでは無く、ファンが「グレイトフル・デッド体験とは何か」を決めたそうです。
要するに、ファンの立場が上でもダメだし、バンドの立場が上でもダメだったんですね。
ファンの位置づけをバンドと対等にして扱い、「自分たちが行っているサービスをどういうものであるかを決めてくれるのは、ファンのコミュニティだ」という事であり、仕掛けてる側が考え方を押し付ける事は不可能であると教えてくれるのです。
【第1回目の総括】
グレイトフル・デッドは従来常識とされていた、レコードを売って収益を上げる考えを正反対に覆し、ファンとのコミュニティを構築し、ライブで収益を上げる事に成功しています。それは、このバンドが、第一にファンの事を考えて行動し、その行動をファンが感じ取る事で強い絆が生まれて行ったのですね。
バンドとファンが同じ立場で関係を築き、バンド側が管理を「ゆるくする」事で爆発的にファンが増えて行った事も興味深いですね
ライブも即興が80パーセントということで、ほぼ毎回違うパフォーマンスが観れるという事にもライブバンドとして成功する事が出来たのでしょう
自分の解釈ですが、このバンドのサウンドは、夕暮れ時に焚火をしながらウイスキー片手にゆっくり聞いたり、
サーファーが波乗りに向かう時に今日の波を予想しながらビーチへ向かう時なんかに非常にマッチしそうな感じが致しますね!(完全妄想)
とにかく噛めば噛むほど味の出るバンドですので、是非ユーチューブご視聴下さい
【追伸】
これからも皆様に有益なブログ運営を続けて参ります
この記事を見て頂いてる方でSNSで拡散しても良いよと思って頂いた方がいらっしゃいましたら、是非 助さん・拡散お願い致します--- (寒-)
(寒-)
次回は未定ですが、グレイトフル・デッドのマーケティング取り上げてみたいと思います
【グレイトフル・デッド選出ランキング】
ローリング・ストーンの選ぶ「歴史上最も偉大な100組のアーティスト」 57位
1994年 「ロックの殿堂」入り
ローリング・ストーンの選ぶ「歴史上最も偉大な100人のギタリスト」
2003年は第13位 2011年の改訂版 第46位選出 ジェリー・ガルシア
全アルバム総売り上げ枚数 3,500万枚